論文翻訳・学術論文翻訳・学術翻訳ユレイタスは、翻訳サービスの国際規格ISO17100認証の取得企業です。さらに、情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC27001:2022)ならびに品質マネジメントシステム(ISO9001:2015)において、優れた社内体制を整備されている企業に与えられる国際規格ISOを取得しております。お客様の原稿を厳重な管理の下で取り扱い、論文翻訳などあらゆる翻訳の品質を高め、維持する仕組みを備えています。

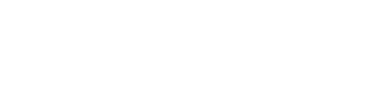
1956年、日本が国際連合に加盟した直後日本人として初めての国連職員になった明石康氏。日本政府国連代表部の要職や国連幹部ポストを歴任しカンボジア和平や旧ユーゴスラビア紛争の解決に取り組んだ。各国の代表が集まり、意見をぶつけ合う丁々発止の国連の場。代表者の発言の一つ一つが、たちまち海を越え、関係各国に届き、分析され、それに応じた政策決定がなされる。コミュニケーションに齟齬があれば国としての信用や国益を失うことにもなりかねない。発言が世界中の注目を浴びる立場で明石氏は、どのようなことを心がけて英語を使ってきたのだろうか。
秋田弁と標準語との壁に悩まされた若き日の思い出から国連での重要な会議でのやりとりまで、日本政府代表として、また国連の幹部としての「ことば」との付き合い方をうかがった。
編集=古屋裕子(クリムゾンインタラクティブ)

戦争が終わったとき、私は旧制中学校の3年生。生まれ故郷の秋田県にも進駐軍がどかどかとやって来まして、中学校の校舎は接収されました。
英語を学び始めたのは中学校からですが、私はあまり好きではありませんでした。なにしろ敵国の言語でしたし、戦後は「ギブ・ミー・チョコレート!ギブ・ミー・チューインガム!」と叫びたいために英会話を学ぶ若者たちを軽蔑したりもしていました。
ただ、私が通っていた秋田中学は県立の中学としてトップクラスで、いい英語の先生がたくさんいたんです。また、私の兄がすすめてくれた参考書がとてもわかりやすく書かれていて、英語には次第に親しむようになってきました。
高校は旧制の官立山形高校に進みましたが、この学校には、『岩波英和辞典』を編さん、執筆した田中菊雄先生がいらっしゃって、私は直接教わりました。田中先生は独学で英語を勉強された方で、今思うと非常に奇妙な発音の英語を話されていましたが、英語の基礎的な構造や文法、語彙について正しい知識を教えてくださいました。
ここに、英文学者の行方昭夫さんという人が書いた『英文快読術』(岩波書店)という本があります。その中に、行方さんが東京大学の2年生だったときに受けた、文化人類学の授業のことが書いてあります。どんなことが書いてあるかとういうと…。
その授業の担当教授は海外から来た人だったので、授業はすべて英語で行われた。従って、生徒が授業の内容を理解するのは、大変な苦労だった。中には、はじめの「Good morning」と最後の「Good bye」しか理解できない者もいた。そのひとりは、新潟の雪深いところから出てきた小和田という男で、もうひとりは秋田の山の中から出てきた明石という男。ところが、ふたりとも中学、高校で英語の基礎だけはきちんとやってきたらしく、その授業に半年も通ううち、先生の言うことをほとんど理解できるようになっていたー。
実はこの本の著者の行方さんは私のクラスメートで、秋田の明石というのは私のこと。新潟の小和田というのは、雅子妃のお父さんであり、国連大使、外務次官などを経て、国際司法裁判所の判事をやっている小和田恆さんのことです。要するに、中学、高校時代までにしっかりした基礎を身につけておけば、その後はヒアリングやスピーキングにも応用できるという例として、私たちが引き合いに出されたわけですが、私は行方さんの考えに賛成しています。
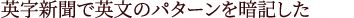
そうはいっても、大学生時代の私が完ぺきな英語を書いたり話したりできるようになっていたかというと、そんなことはありませんでした。
当時から東大には海外から来た教授が何人かいて、私はある先生が主催するお茶会によく顔を出していました。お茶会では、先生のきれいな二人の娘さんやアメリカ人青年が何人か集まっていて、お茶会に参加するうちに彼らと親しくなって、政治の話、社会の話、国際政治の話などをするようになっていたんです。
ときには口角泡を飛ばして議論をしたこともありました。当時の日本の学生のほとんどはマルキシズムに傾倒していたので、アメリカ人の青年たちから見ると、私たちが共産主義者のような経済用語を口にしているのが面白くなかったんでしょう。「あなたたちは共産主義者なのではないか」と聞いてきたんです。もちろんすぐ懸命に説明しましたが、そのころの私の語学力では、思っていることを完ぺきには伝えられませんでした。もどかしかったですね。
そのもどかしさが原動力となって、英字新聞を読んで英語を学ぶようになりました。とくに社説の表現は参考になりました。英文にはパターンが無限にあるわけではなく、いくつかのパターンを暗記して、そのうちの一つを使えばいいわけだ、そういうことが徐々にわかってくる。たとえば、言いたいことを表現する前に、「This is clear that-」「It seems to me that-」などと前置きすると、その間に頭の中を整理して話せることもわかってきました。

大学生活を通じて「国際政治学の学究になる」という目標をもった私は、フルブライト奨学金制度に応募して合格、バージニア大学に留学しました。
1955年のことです。横浜の港に今もつながれている氷川丸という船に乗って、十数日かかってアメリカにたどり着きました。アメリカという国にじかに触れることのできるときめきと、一抹の不安こそあれ、フルブライトの狭き門を通ったことで英語力にも少しは自信があり、期待感に満ちていました。
ところが、バージニア州には南部の独特のなまりがあり、初めのころはそれを聞き取るのに苦労しました。
スラングにも手こずりました。私は学生寮に入って、アメリカの学生と一緒に生活しましたが、彼らの会話に差し挟まれる、Fで始まる4文字が理解できない。「『FUCK』とは、どういった概念を言い表す言葉ですか?」なんて聞いて、笑われたりしました。スラングは学校教育で学んだことがないし、辞書にも載っていないから、そうやって笑われたり、馬鹿にされたりしながら覚えるしかありませんでした。
でも、決して卑屈にはなりませんでした。アメリカの学生たちとセミナーで議論したり、寮でわいわい騒いだりする程度のコミュニケーションができるようになると、彼らがゲーテとかジードとか、当時の日本の大学生が常識として持っていた小説家や哲学者の本を読んでいないばかりか、名前すら知らないことがわかったんです。知識や教養はこっちのほうが上だぞと、内心自信を持ちました。
ちなみにフルブライト奨学金というのは優れた奨学金制度で、大学の授業料を免除してくれるだけでなく、当時の金額で月に140ドルを支給してくれました。そうはいっても、中古の車を買おうにも満たない程度の金額で、近所の女子大学に車を乗りつけて女の子と遊びに行くなんてことはできませんでしたが、かわりに毎日図書館に通いつめて、夜の12時まで勉強しました。日本にいたころは苦学生でしたから、アルバイトをせずに心おきなく勉強できるというだけで幸せでした。
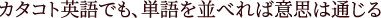
1956年12月、日本が国連に加盟することになり、私は翌年の2月からそこで働くことになりました。
そのころの私の英語力は、イギリス人の上司に「きみの英語はアメリカ人よりはましかもしれないけど、イギリス人の英語に比べると全然だめだよ」と言われる程度のものでした。ほめられたんだか、けなされたんだか、今でもよくわかりませんけれど(笑)。
最初に手がけた仕事が、1956年10月に起こったハンガリー動乱に関する事務総長報告書をまとめる仕事です。共産党が支配的な地位を占めるハンガリー政府に対して、民衆が全国的規模で決起し、ソ連の軍事介入によって鎮圧された大事件です。
その報告書を作るにあたって、14、15人のスタッフが集められました。国籍はみなばらばらで、12、13カ国にわたっていたと思います。当然のことながらコミュニケーションには英語を使います。イギリス人やアメリカ人だけなら問題ないでしょうけど、中には英語を第2外国語、あるいは第3外国語、第4外国語として学んできた人たちが入り混じっているわけで、私を含め、なまりの強い英語の人がほとんど。そんな集まりで意思疎通するのは大変です。
ただ、国連には国際政治にまつわる独特の専門用語があって、文法は不完全でも、単語をつなげていけばだいたいの意思は通じることがわかりました。何よりも、いついつまでに報告書を仕上げなくてはならないという共通の問題意識があったことが大きい。毎晩遅くまで膝をつき合わせ、週末にも出勤して協力し合ったことで、チームワークが築けました。その結果、質の高い報告書を作成することができて、私の中でもこれでやっていけるという自信が生まれました。

国際的な官僚や外交官にとって、仕事の一番大事な道具は「ことば」です。とくに国連では、各国の代表としていろんな委員会で「おれの意見が正しい」「いや、おれの方が正しい」と丁々発止のやり取りが交わされます。誤解を生まないように言葉が正しく使われなければならないし、言葉は意思疎通の手段であると同時に、相手をぐさりと突き刺す武器でもありうる。いろんな国の人が集まっているから、使う英語の語感も違う。
私は国連代表部にいて日本政府代表をしていたとき、いろんな国の人に理解してもらうために心がけていたことがいくつかあります。
まず、モットーとしていたのは、頻繁に発言すること。国連の会議の場では、5、6カ国が発言すると、あとはだいたい発言内容は似たりよったりになります。聴衆に聞いてもらうためには、3番目から4番目くらいまでに発言しないとだめ。発言順序が遅くなるほど印象が薄いんですよ。そのためには議題に関して予習復習が欠かせないし、議場で議論をよく聞いて、各国がいま何を考えているか、何を目的としているか、何を心配しているか、大きな流れはどういう方向に向かっていて、その中で日本の利害関係はどこにあるか、ということを常に理解していなければなりません。
そしてもう一つ、感情的なケンカはご法度。相手を正面切って批判しない。できるだけ婉曲に、ニュアンスや皮肉などをうまく使い、もし相手が怒り心頭に発したら、相手が過剰反応して一人相撲を取っているように見せることで、相手の上に立つようにする。これは技の勝負です。感情的になると負けなんですよ。相手を説得するためには、冷静に、論理的に議論を推し進め、裏づけとなる客観的な事実や統計学的なデータをたっぷり持っていないと、誰も聞く耳を持ってくれません。

また、場面に応じて英語に「味付け」を考え、大きな会議では味を心持ち強くさせることも時には必要です。あいまいでぼんやりした表現では、忙しい各国代表の人たちに注目してもらえません。
一度、こんな出来事がありました。国連の日本代表部で、国際協力機構の理事長でいらっしゃる緒方貞子さんが国連総会の第3委員会、私が第5委員会を担当していたときの話です。緒方さんが第3委員会のメンバーから、第5委員会の日本代表が女性の地位についてちょっと変なことを言っているという噂を聞いたらしくて、私の部屋に駆けつけて来られたんです。そして「明石さん、いったい何を言ったの」と詰め寄られました。
私は、国連にもっと日本人職員を増やせという趣旨で、多少どぎつく「国連職員の資格要件を満たしているんだったら、国連憲章101条に従って、日本のように職員数のまだ少ない国の場合、男性とか女性とか言わず、職員を採用することが決定的に大事なことである」と演説したところ、第3委員会は女性の代表が多かったために、「明石は女性職員を増やすことに反対らしい」と曲解されたんです。これは女性に対する差別発言ではなく、女性の社会進出が遅れているアジアの実情を考慮しなければという配慮に基づいて、発言の味付けを多少きつめにしたために予想以上の反響が返ってきてしまった例ですね。

それから、非常に重要で微妙な交渉の場では、できるだけ一対一で話すことも心がけていたことの一つです。
これは、ボスニア紛争が激化した1990年代のころの話です。旧ユーゴ問題担当・事務総長特別代表に任命された私は、1994年のゴルジデ事件の折、セルビアのミロシェビッチ大統領と会談することになりました。セルビア人側が必要な譲歩をしないならば、NATOによる空爆を大規模な形で行わなくてはならない。セルビア民族が絶滅に瀕するだろうことを手厳しく言って、譲歩を迫った緊迫した局面です。
国連側からは10人、セルビア側は20人くらいの大人数で、議場はひしめいていました。そこで私は大統領に、「できれば私とあなたと二人でお話できませんか?」と提案しました。大統領にもメンツがありますから、自分の仲間や部下がまわりにいると、なかなか本音で話をすることができないだろうと判断したんです。
さすがに一対一というわけにはいきませんから、あちら側は大統領と、セルビア人勢力のシビリアンの代表と軍人の代表が同席し、私は国連PKOの総司令官だけを連れてミロシエビッチ大統領の執務室に入り、セルビア人の歴史の分岐点にいま立っていることを率直に語り、大事な譲歩をかち取ることができました。
もう一つの例ですが、カラジッチ代表とのツヅラ空港開港をめぐる会談のとき。最初、態度を硬くしていたカラジッチ氏を説得するには、どうすればいいか。彼の冗談好きを知っていた私はこう切り出しました。
レディがノーと言った場合、それは「Maybe」くらいの意味だ。レディが「Maybe」と言ったときは、「Yes」という意味だ。しかし、レディが「Yes」と言うなら、その人はレディとは言えない。外交官が「Yes」と言うとき、これは「Maybe」くらいの意味だ。「Maybe」と言うときは、「No」の意味だ。しかし、外交官が「No」と言うならば、彼は外交官とは言えない。ひるがえってあなたは、国家を背負う大外交官なんだから、私に対して「No」と言えるはずはない、と。
用意していた言葉ではなくて、とっさに出てきた言葉でした。すると、カラジッチ代表はカラカラと笑って、「ミスター明石はこういうことを言っている。意地を張るだけ損だ」と、まわりを説得し、少なくともその日はツヅラ空港の開港に「ノー」とは言わなかったのです。

言葉を使いこなすには、ときには恥をかきながら経験によって磨いていくしかありません。私もすんなりとバイリンガルになったわけではなく、腹立つ思いもたくさんしたし、たくさん恥もかきました。
私にとって、第1外国語は、実は東京の標準語とも言えるでしょう。大学に通うために秋田から上京して、最初に苦労したのが言葉でした。秋田弁がまわりの人にまったく通じないんです。最初の下宿は、杉並区の永福町。冬になって寒かったものだから、下宿の大家さんに「おばさん、火をください」と頼んだとき、おばさん、ケタケタと笑い出しましてね。何がおかしいのかなと思って怪訝な顔をしていたら、おばさんには「へをください」と聞こえたそうなんです。恥ずかしかったですね。
電車で乗り換えの仕方を聞いたり、道を聞いたりしても、当時、東京の人は私の言葉を理解できませんでした。下手に口を開いたら笑われるのが怖くて、人前では口をつぐんでしまうことが多かったです。

私は初代のトリグブ・リー氏を除いて、すべての国連事務総長と面識がありますが、皆さん立派に英語もフランス語も話しましたけれども、お国なまりが残っていました。スウェーデン、ミャンマー、オーストリア、ペルー、エジプト、ガーナ、韓国と、それぞれに独特のなまりを持っています。けれども歴代総長はそのなまりを気にせず、理性的に話していました。ネイティブスピーカーほど完ぺきではなくても、総長の言うことの95%は誰にでも理解できただろうし、総長もほかの人の言うことの98%は理解できたでしょう。
言葉というのは、それでいいのだと私は思うんです。
なまりのない英語は、魅力がありません。なまりはそれぞれの人のアイデンティティであり、現代のようにグローバル化が進行した世界では、アイデンティティを主張することはむしろ注目すべきことです。
その点、日本人は完ぺき主義というかメンツを重んじるせいか、自分のなまりを気にしすぎます。私も秋田弁が恥ずかしくて尻込みしていた時期があるから、恥をかきたくない気持ちはわかりますが、躊躇があってもそれを克服して、勝負は内容でやるのだから、表現は「自分なりの英語でやる」と腹をくくることが大事だと思います。

私は毎年、群馬県庁と教育委員会の主催で、優秀な高校生を10人えりすぐり、国際人を養成する「明石塾」という研修に取り組んでいます。そこで学生を見ていると、ものごとをよく考える学生ほど自分が思索していることを言葉に言い表せなくて、いらいらしているんですね。
私には、言いたいと思っても言葉が未熟で言えない学生のもどかしさがよくわかるし、それを克服するならば、より高い次元に進んでいけると思うんです。
自分の中に語るべきことがない人は、言葉を勉強したってしょうがない。英語を学習する動機も、そうあるべきではないでしょうか。何か情熱的に知りたいこと、語りたいことが自分の中にあり、同じようなことを世界の人から学びとるために、外国語を学べばいい。あなたがインド文化について関心を持っているのであれば、インド文化について書かれたものを英語で読破すれば、英語力は副産物として身についてきます。
英会話において、私たちは逆立ちしても、アメリカの子どもにもイギリスの赤ん坊にもかないません。また、そういう勉強をやる必要もない。自分にきちんとした教養があり、何か自分の熱く語れる世界や物の見方とかを持っているならば、たとえ英語はカタコトでも相手にすごいなと思わせることは可能だし、自分の下手な英語にも懸命に聞き入ってくれるはずです。
ただ楽しく英会話ができればいいとか、「英語力をつけること」だけを目標として英語を勉強する人たちは、それだけではさびしいと思うんです。
人間と人間の相互理解、真剣勝負の対話には、語学力も大事ですが、それは二義的なもので、自分の知識や教養、世界観とか、人生に向き合う真剣さだとか、そういうすべてをひっくるめて、人間としての総合力が問われることを忘れてはならないと思います。

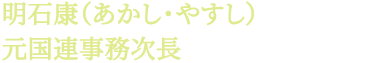
1931年、秋田県生まれ。54年、東京大学教養学科卒業。同大学院を経て、バージニア大学、フレッチャースクール、コロンビア大学に留学。57年、日本人として初めて国連事務局での勤務を始める。政務担当官、事務総長官房補佐官、職員組合委員長、日本政府国連代表部の参事官、公使、大使などを歴任。92年から95年までは、事務総長特別代表(カンボジア暫定統治機構、旧ユーゴスラビア担当)に就任。97年末、国連を退官してからは、スリランカ平和構築担当日本政府代表、明石塾塾長、神戸大学特別顧問、金沢大学特別教授などを務める。主な著書に『国際連合―軌跡と展望』(岩波書店)、『戦争と平和の谷間で 国境を超えた群像(岩波書店)』など。